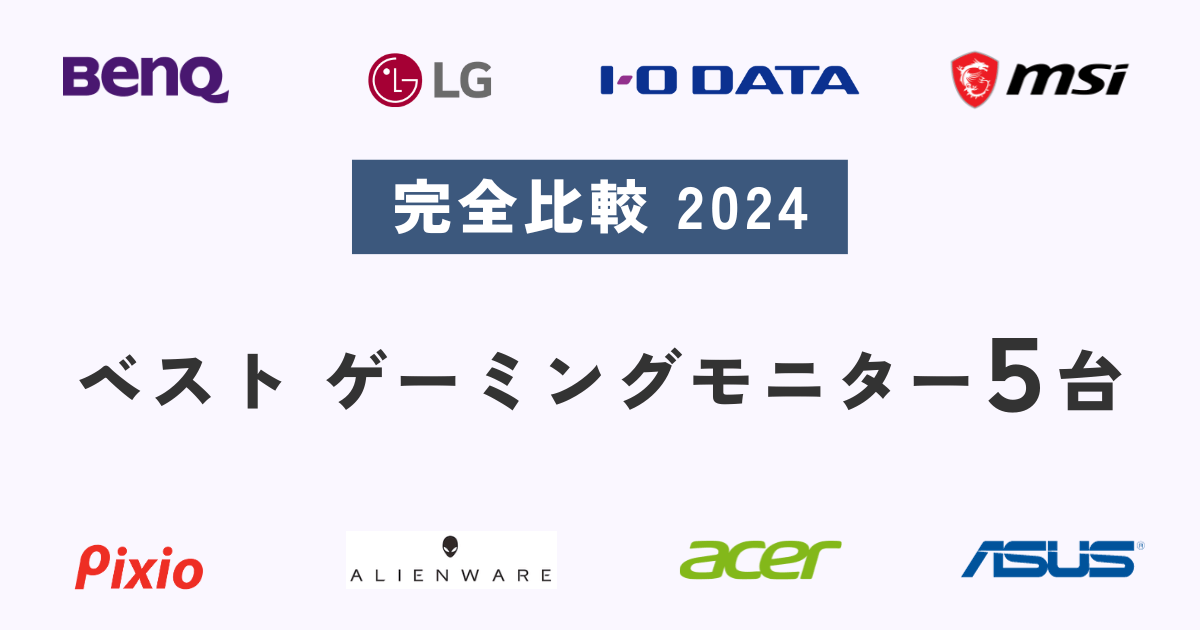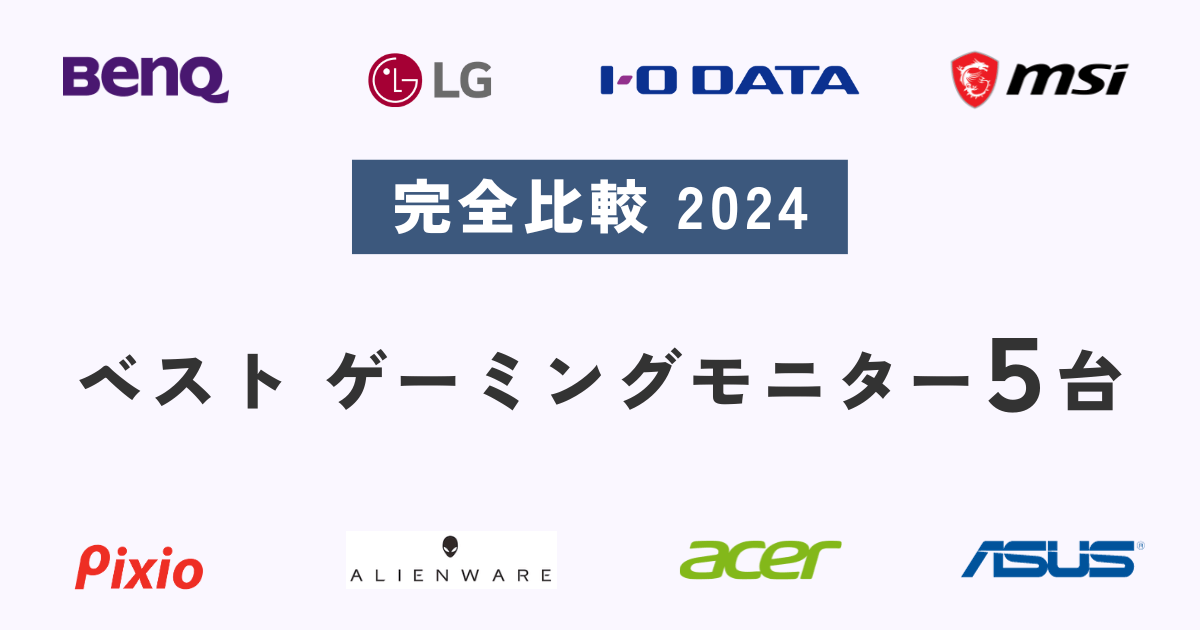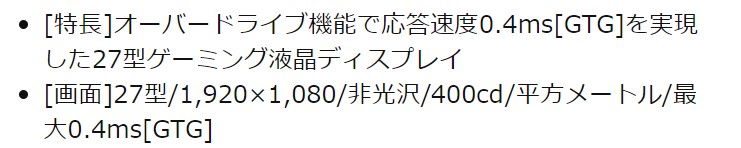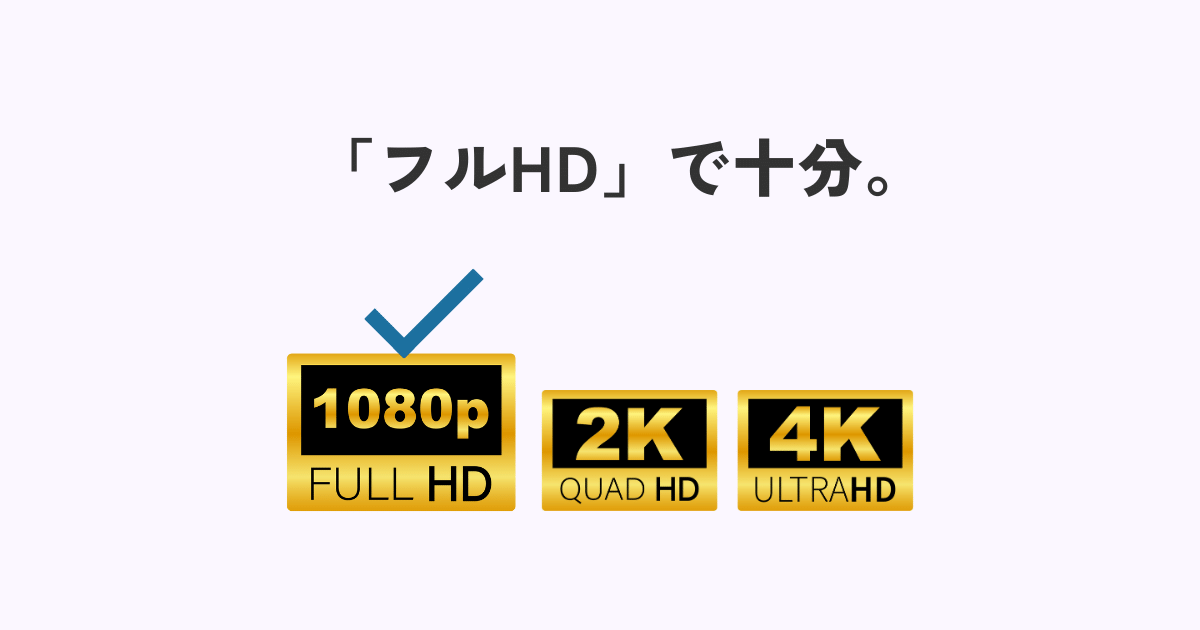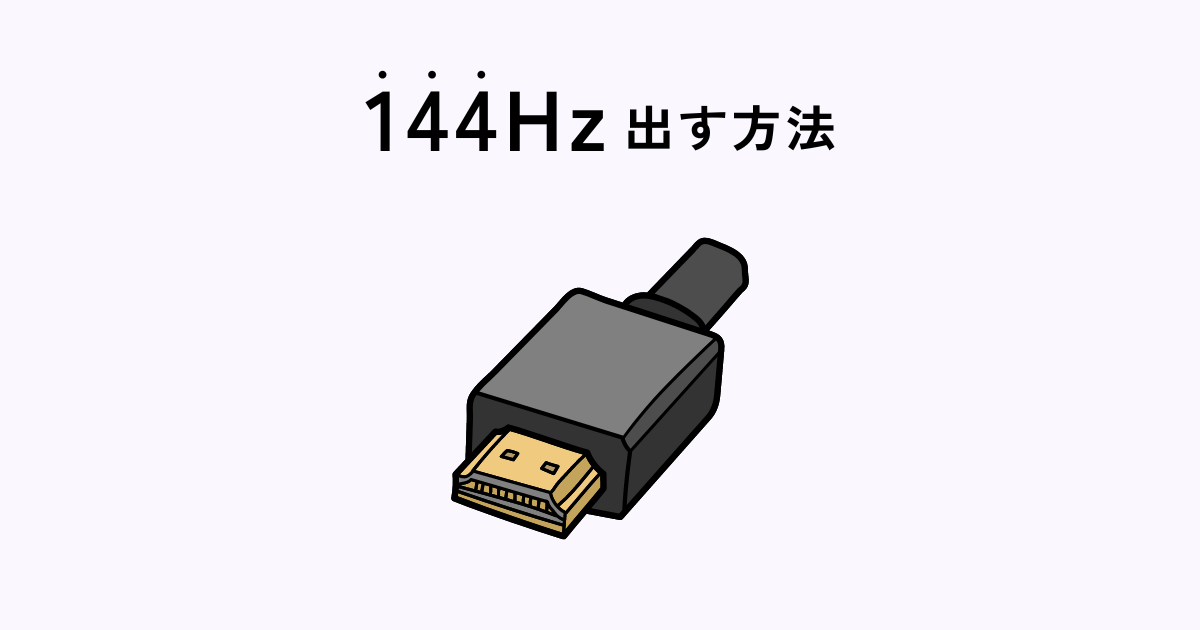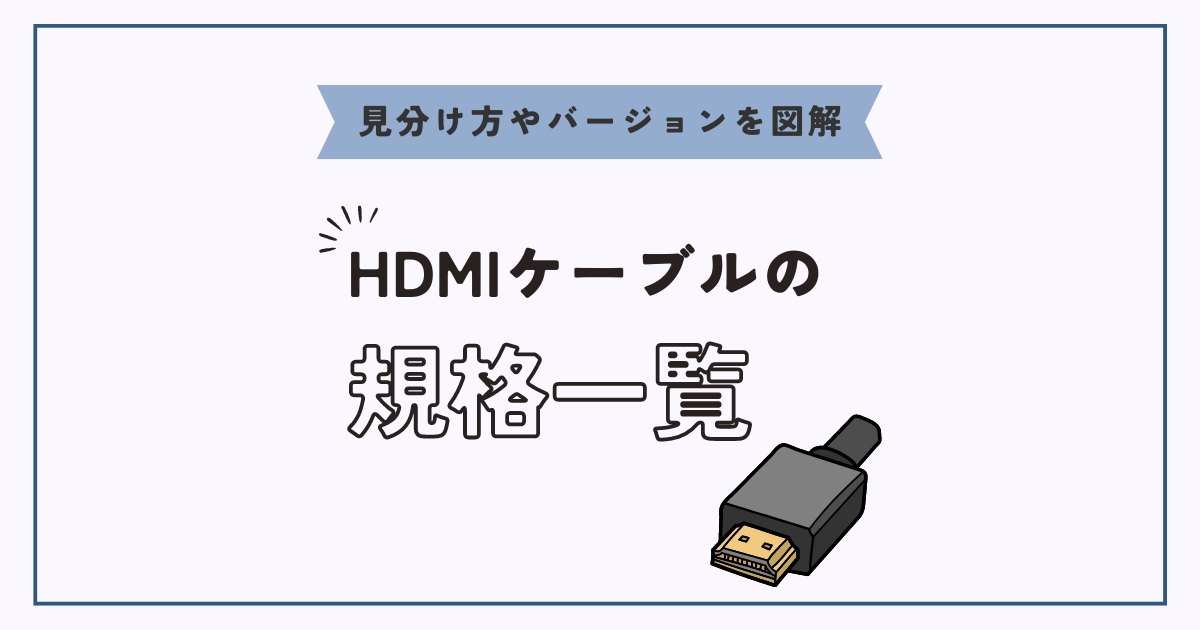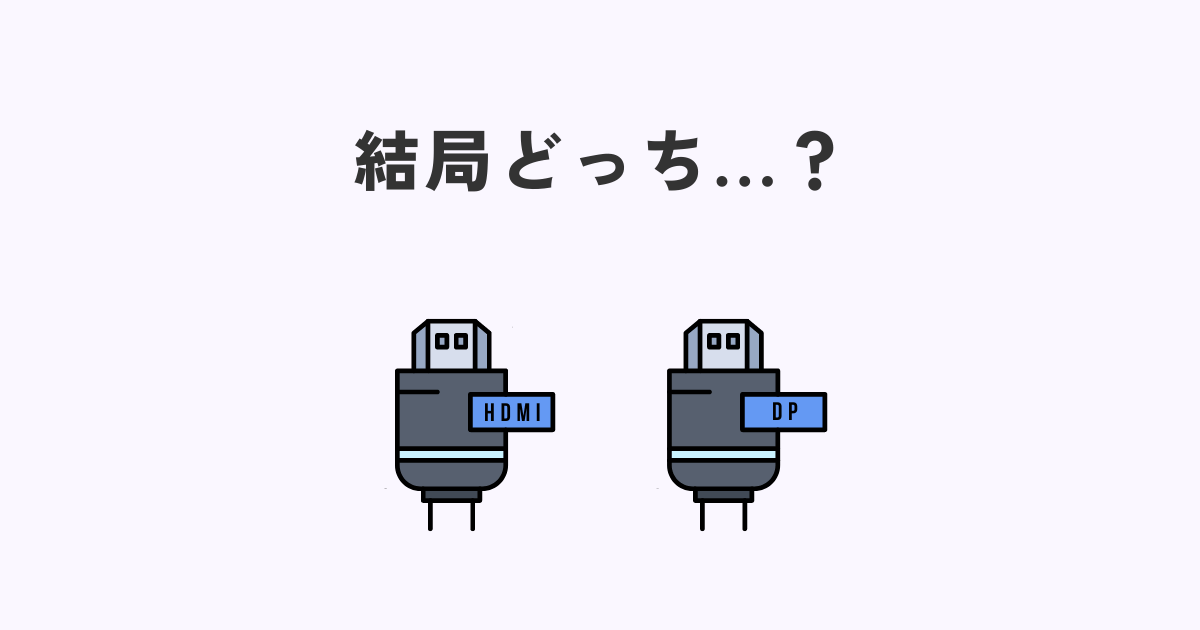オーバードライブ機能ってなに?
オーバードライブすると、映像にどんな違いがでるの?
こういった疑問を解決します。
モニターのオーバードライブとは?
オーバードライブの仕組みと弱点。
「オーバードライブ」の仕組みは簡単です。
サクッと理解してゲーミングモニター選びの参考にしてみてくださいね。
モニターのオーバードライブとは?


モニターのオーバードライブとは、超カンタンに言うと「映像のブレを減らす技術」です。
少し詳しくすると、中間色層での応答速度を高速化し、映像の残像感を減らす技術になります。
「モニター オーバードライブ」で検索して本記事を読んでいただいている人なら、上記でピンときてるかもです。
意味不明って人でも大丈夫です。解説していきますね。
ちなみに、オーバードライブ搭載のモニターは、こんな感じで表記されています。
オーバードライブが応答速度の高速化につながっているのが、分かるかと思います。
オーバードライブを知る前に
オーバードライブを理解する前に知っておくべきは、「応答速度」についてです。
下記が分かればOKです。
応答速度とは、「映像の色の切り替わる速度」のこと。
応答速度は、「映像の色の鮮明さ」に直結する。
上記が分かればOKです。
オーバードライブの仕組み
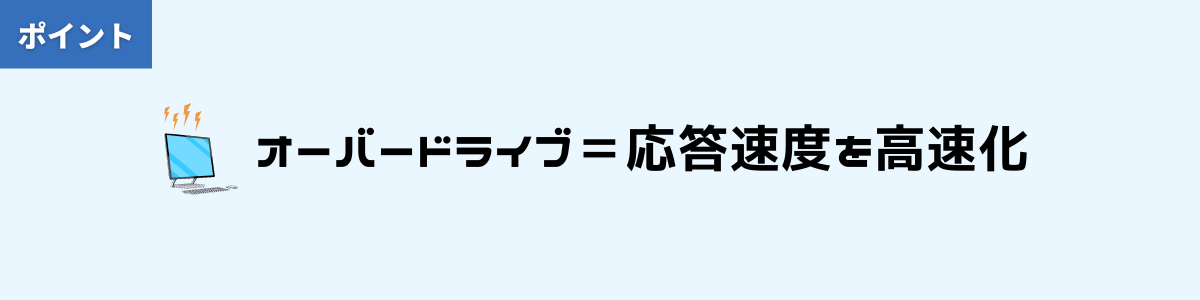
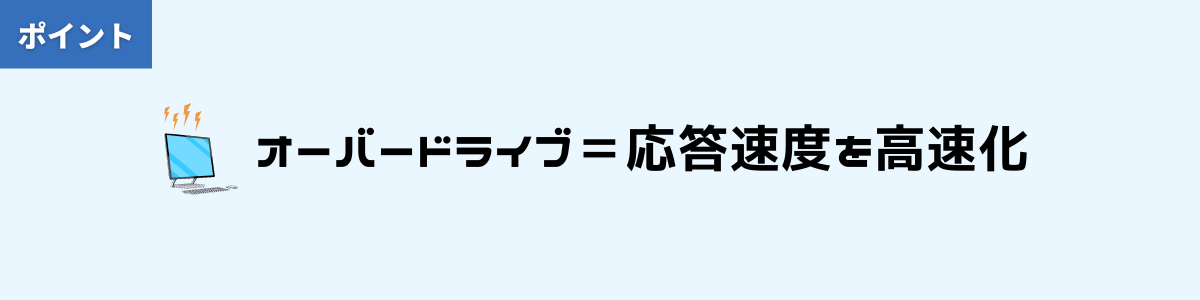
オーバードライブとは「応答速度を高速化し、映像の残像感を減らす技術」です。
具体的は技術は、下記のとおりです。
液晶分子にかかる電圧を、通常よりも大きく変化させ、色の変化も高速化させています。
(以下少し難しいですが、ゆっくり読んでみて下さい。)
液晶モニターの色というのは、液晶分子に加える電圧の変化で表示する色を変化させています。
この電圧を加える回路に、オーバードライブ回路を用いることで、通常より大きく電圧を変化させ、モニターの応答速度を高速化させることができます。
電圧と色の変化図
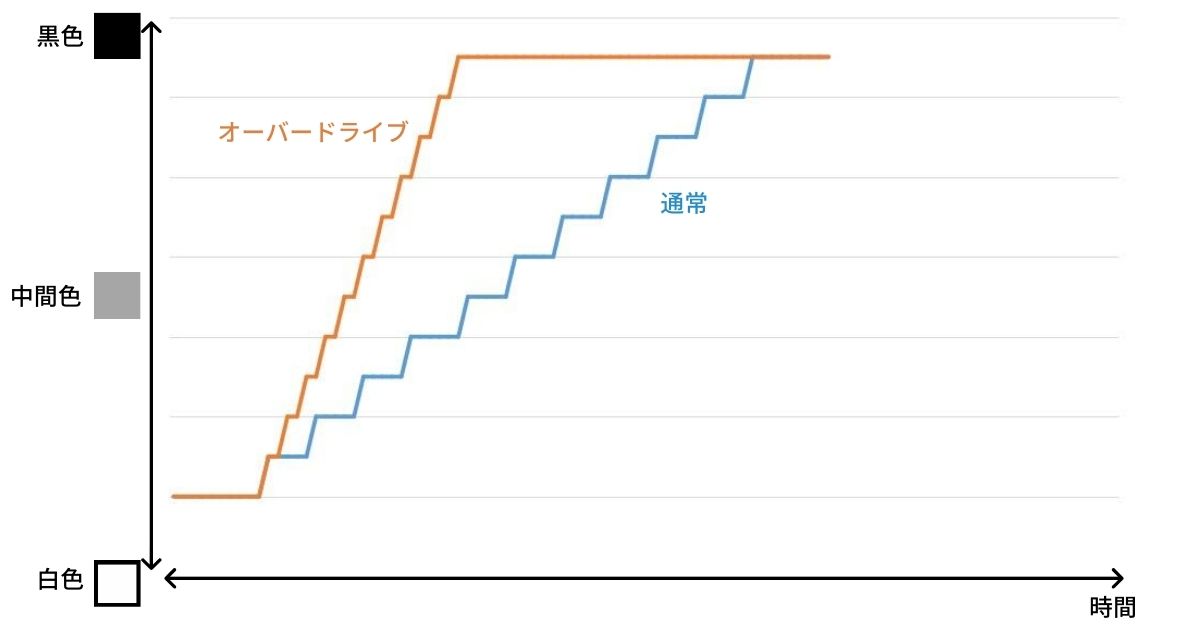
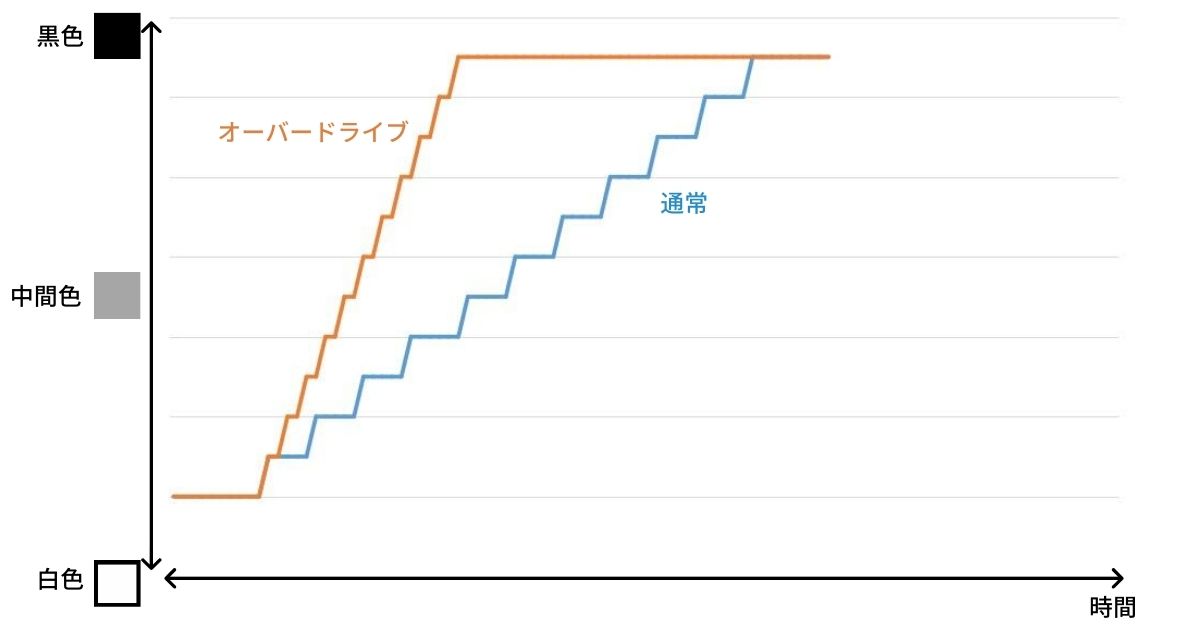
オーバードライブの方が、電圧の変化が速く、目的の色までの変化速度(応答速度)が速くなります。
モニターのオーバードライブの弱点


次にオーバードライブのデメリットについて見ていきます。
デメリットは、オーバーシュート(アンダーシュート)です。
オーバーシュートとは
オーバーシュートとは、色の変化時に、例えば、電圧30→70の際にオーバードライブが強いと、電圧30→75→70と瞬間的に、その色を超えた電圧がかかってしまうことです。
下記の図が分かり安いです。
電圧と色の変化図
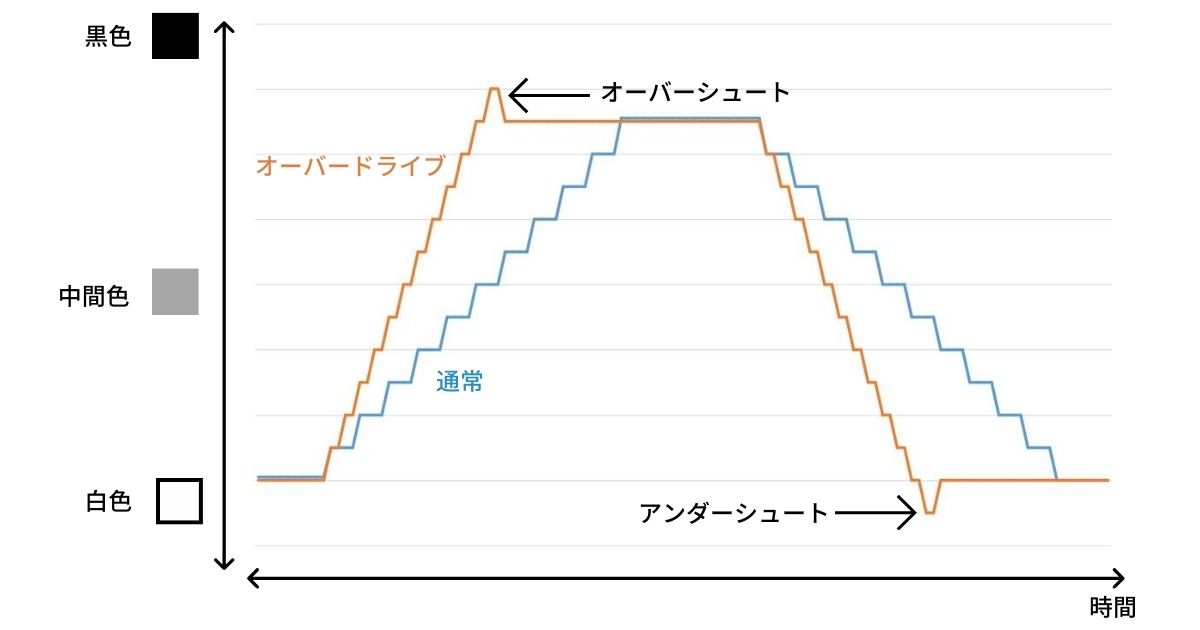
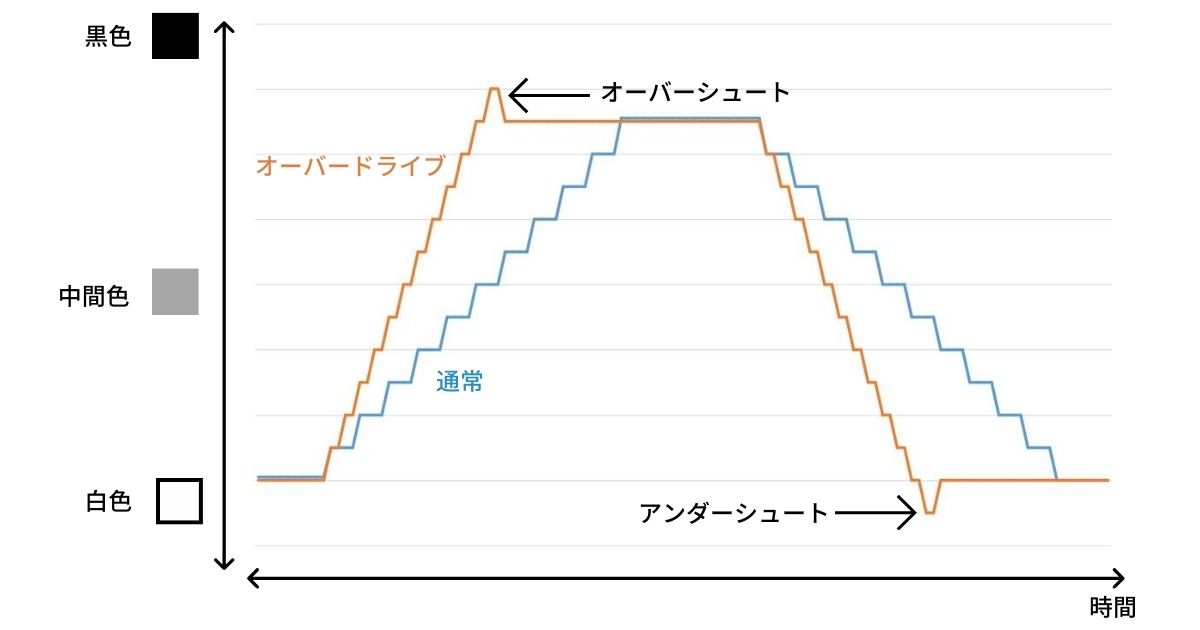
オーバーシュート(アンダーシュート)を図で表すと上記のとおりです。
とはいえ、ぶっちゃけ、オーバーシュートはわからないです…。
デメリットと上げながらも、正直オーバーシュートって、映像見てて、絶対分からないです。
超スローモーションで目をギンギンにこらしてみても、人間にはわからないですね。
オーバードライブの効果については、映像見ててしっかりわかるので、メリットの方が大きいです。(当たりまえですが…。)
» オーバードライブ搭載のゲーミングモニターを見てみる。
【まとめ】モニターのオーバードライブ
本記事のまとめは、以下のとおりです。
オーバードライブとは、「液晶分子にかける電圧の変化を大きくし、応答速度を高速化させ、映像の残像感を減らす技術」
デメリットも仕組み上あるが、実際は無いも同然。
上記のとおり。
最後にですが、オーバードライブ機能の有無はゲーミングモニター選びにあまり関係なかったりします。
ゲーミングモニターを探している方は、下記の記事をどうぞ。